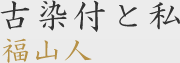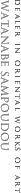
天啓の染付を、我国では俗に「古染付」と呼んでいるが、それは何時頃、誰によって名付けられたものか、判然としない。当時以後の茶会記や陶書関係のどこを見ても、その名は見当らないのである。
単に「古染付」という三文字から汲みとれる感じでは、古い染付という意味にとれ、これは新渡りの染付に対し、古渡りの染付の意として用いられたのではないかと思われる。いずれにしても、その時期は現世に至ってからで、せいぜい っても百年位ではなかろうか。
しかし、「元」に始まったといわれる染付が、「明」に入って宣徳、成化、嘉靖、万暦、天啓、崇禎と続き、それぞれの時代の作風が、見を競って咲き誇った中で、どうして天啓の染付だけが「古染付」と呼ばれたものか。
その を解く鍵は、やはり茶方の註文による日本向特別品という意味合にある様だ。そして、数ある染付の中で、特に天啓染付だけを別に呼称したのは、その風雅な作風を重んじ、他の時代の染付と敢えて区別した数寄者の慧眼と、粋な心根にあると言わねばならない。

それにしても、天啓染付にこの様な愛称を与へた人の機智もさることながら「古染付」とは正に言い得て妙である。染付へのほのかな郷愁を、これ程 に微妙に匂わした呼び名はあろうか。これが、くだんの李朝陶磁にある無地刷毛目手などという、似ても似つかぬ呼び名でなくて良かったと思うのは、私ばかりではあるまい。まさに古染付は「古染付」の他にないのである。従ってその語源の 索は、これ以上は全く無意味な試みであると言えよう。
古染付の生まれた天啓(一六二一ー一六二七)は、万暦につづく七年間で、約三百年の明朝の歴史の中で、国力の最も衰微した末期に当る。景徳鎮窯業史からみれば、乱世という社会情勢の中で、これ 主役を演じて来た御器 が廃止され、それに代って民窯の活動が一段と盛んになった時期である。
俗に天啓染付と称する一種独特のやきものが生まれて来たのは、この様な時代背景があってのことで、天啓年代に至って突如として出現したものではなく、万暦に るっても既にその萠芽は見られるのである。
唯、官窯が消退したために、その特徴であったものがたさが次第に消えて、勢い民窯の風味が表に出て来、それが古染付の母体となったと推察しうる。従って年代的には、どこからどこ が古染付の出現した時代かは判断とせず、万暦に っても、崇禎に降っても古染付らしい染付は存在するので、莫然とした言いまわしながら、天啓を中心とした明未清初の端境期のやきものとうけとめた方が適当であろう。
さて、この様な生い立ちの古染付は、いかにも中国陶磁の伝統を 笑うかの様に自由奔放で、さり気ない。律義に、しかも均等に余白を唐草模様や雲竜文で埋め尽すような明代の染付に較べ、古染付の絵付は、いかにもおおらかで、屈託がないのである。そこには、こうしなければならないといった制約もなければ、そうなるのが当然といった習慣めいた惰性もない。
例えば、その文様に於て、描線が曲っていようと、いまいと、一本余っても足りなくても、また太くても細くても、一向にお構いなしといった鷹揚さが、反って古染付の古拙ぶりを助長し、その面目を躍如とさせているのである。
また、線描きを主とした幾何様文でも、輪文、網文、麦藁文、石畳文、更紗文など、描線が自由にのびのびとしながらも、決してバランスを崩さず、沃気に満ちた現代陶芸が、どう転ろんでも真似の出来ない風雅を醸し出している。
そこに描かれるものは、山水を始めとして、花鳥、人物、動物、故事、物語など、何事も画題ならざるはなく、あらかじめ意図された意匠がないかの如く、自由でかつ、即興的である。
そして、絵付の展開は甚だ詩情的であり、説話的である。例えば、搭持羅漢図皿(左写真参照)の如きは、中皿という白い空間を、辺縁を描線でひきしめて、たった一人の羅漢がいるだけ。だが、この他に何を描くことがあろうか。古今を通じて、この様な卓抜なデザインは、初期伊万里染付のごく一部を除いては例をみない。羅漢の表情は一見、漫画的であり、しかも象徴的である。それは、圧制から解き放たれた天啓画人の欣びの声ともとれ、また、惰落した現代陶芸への揶揄とも思えるのである。
→2ページへ